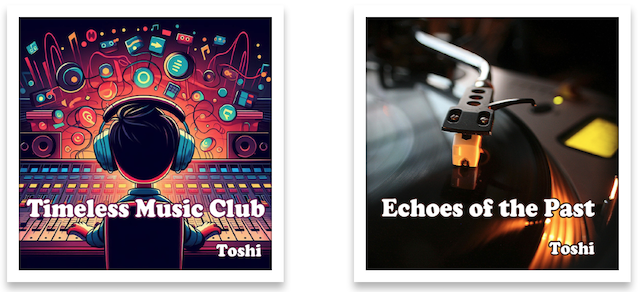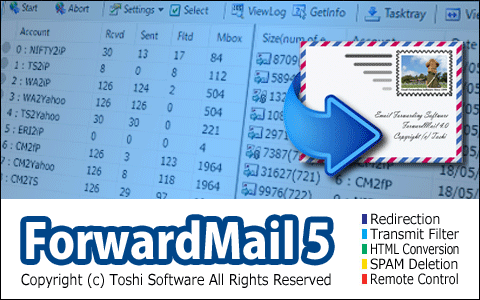スクラッチ設計のコンプレッサー(改):OTA 13600を使って作り直し
2024/11/04
「SSM2164」から「NJM13600」に変更
VCAに使えるデバイスとしては、OTA(トランスコンダクタンスアンプ)がありますが、現在入手できそうなのは、「3080」「13600/13700」です。「3080」はギターのエフェクタによく使われますが、設計が古く、使い方に癖があるため、新しい方の「13600」を使って見ました。このICは、以前「MAD PROFESSOR AUTO WAH」のクローンを自作したときに使ったことがあります。
「13600」は電流動作になっていて、一般の電圧だけ考えれば設計できるオペアンプとは異なります。入力ピンに直列に抵抗を入れて電圧を電流に変換して入力し、出力ではGND間に抵抗を入れて出力電流を電圧に変換します。この抵抗値は「13600」が歪まないようにダイナミックレンジを考慮して決める必要がありますが、これだけ考慮すれば、一般のオペアンプと同様の考え方で使えます。
このOTA「13600/13700」は、もうディスコンになっていて、流通在庫のみのようです。最近のVCAを使うオーディオ機器はデジタル処理になってしまい、この様なアナログデバイスは使われなくなっているのでしょうか?
このOTAを使って、Feed-forward型(入力からコンプレッション制御信号を作る)のコンプレッサ回路を組んでみました。
スレッショルドの回路を変更
そこで、今回は、先に差動オペアンプで全波整流した入力信号からスレッショルド電圧を引き、1/2VDD(この回路の仮想GND)より上に出た部分だけをダイオードで切り取る方法に変えました。精度は高くなったと思います。
ベースを試奏して出音を確かめてみた
黄色(入力信号):ジャズベース直挿し/レベルの粗さが目立ちます 紫(コンプレッション制御信号):OTA13600のゲインに使われる信号 薄いブルー(出力信号):本コンプレッサ通過後:レベルがきれいに揃っています レシオ(圧縮率)はMAXにしていますので、-12dBを超えたレベルはすべて-12dBに抑えられます。そのため、出力の波形(薄いブルー)が全て同じ高さになっています。
下でこのベース演奏(オリジナル曲「My First Funk」のリズム)を聴けます。ブレッドボードですので、電源のスイッチングノイズが乗っています。
コンプレッション、入力レベルのインジケータを追加
入力のインジケータは、レベル検出部の全波整流信号を使い、オペアンプの基本回路でコンパレータを作ってLEDをドライブしました。一瞬のピーク時でもLEDが一定時間光るように、サンプルホールドの回路にしてあります。
他のパラメータを可変できるように このあとは、この回路を維持しつつ、以下のパラメータを可変できるようにして、特性を測定してみようと思います。
Attack Time Release Time Ratio(回路に実装済ですがMAXで試しました) AttackとReleaseを決めるサンプルホールド回路のCR(回路図中のC14、R21)は、前後のインピーダンスの影響を受けないようにオペアンプで挟んであります。ここを変化させて、来週にでも特性を計って見たいと思います。
(2024/12/11 追記)