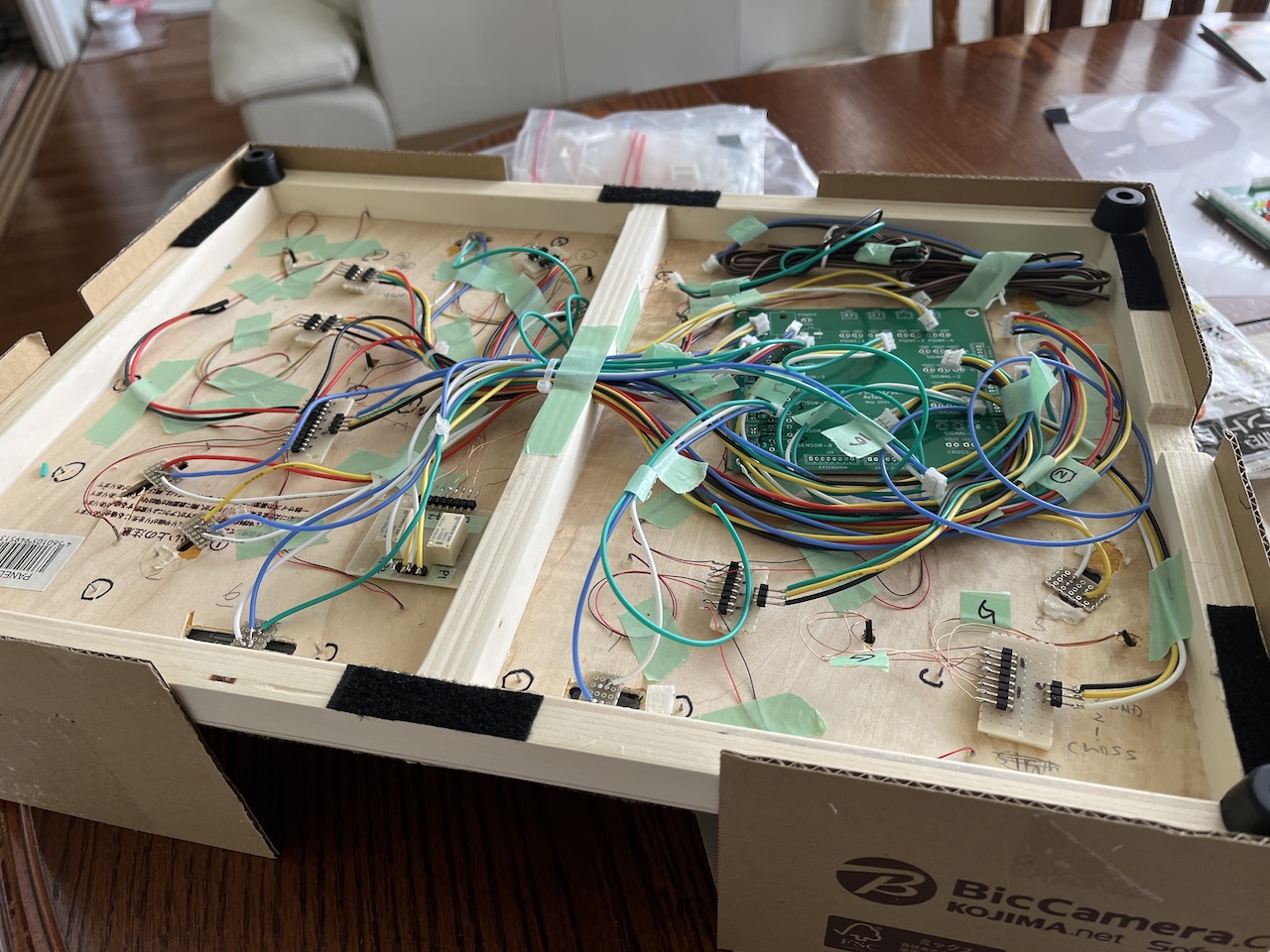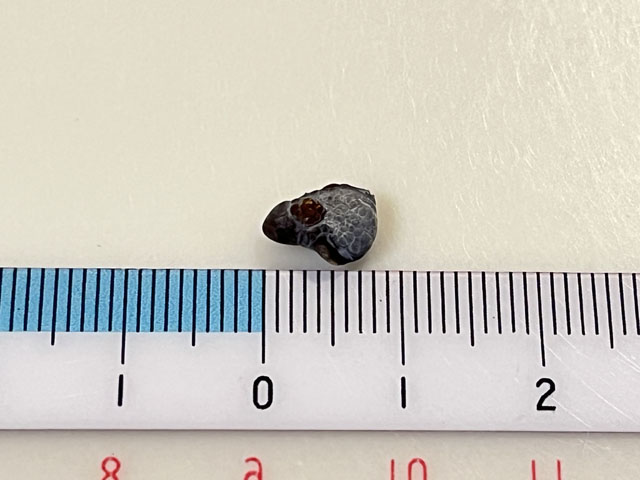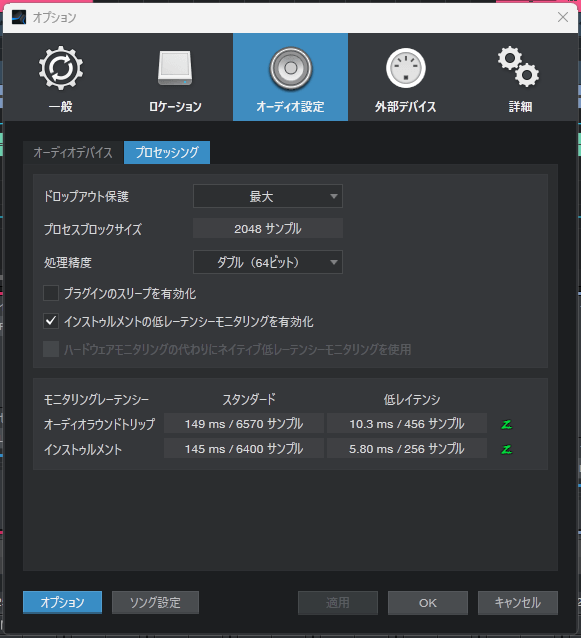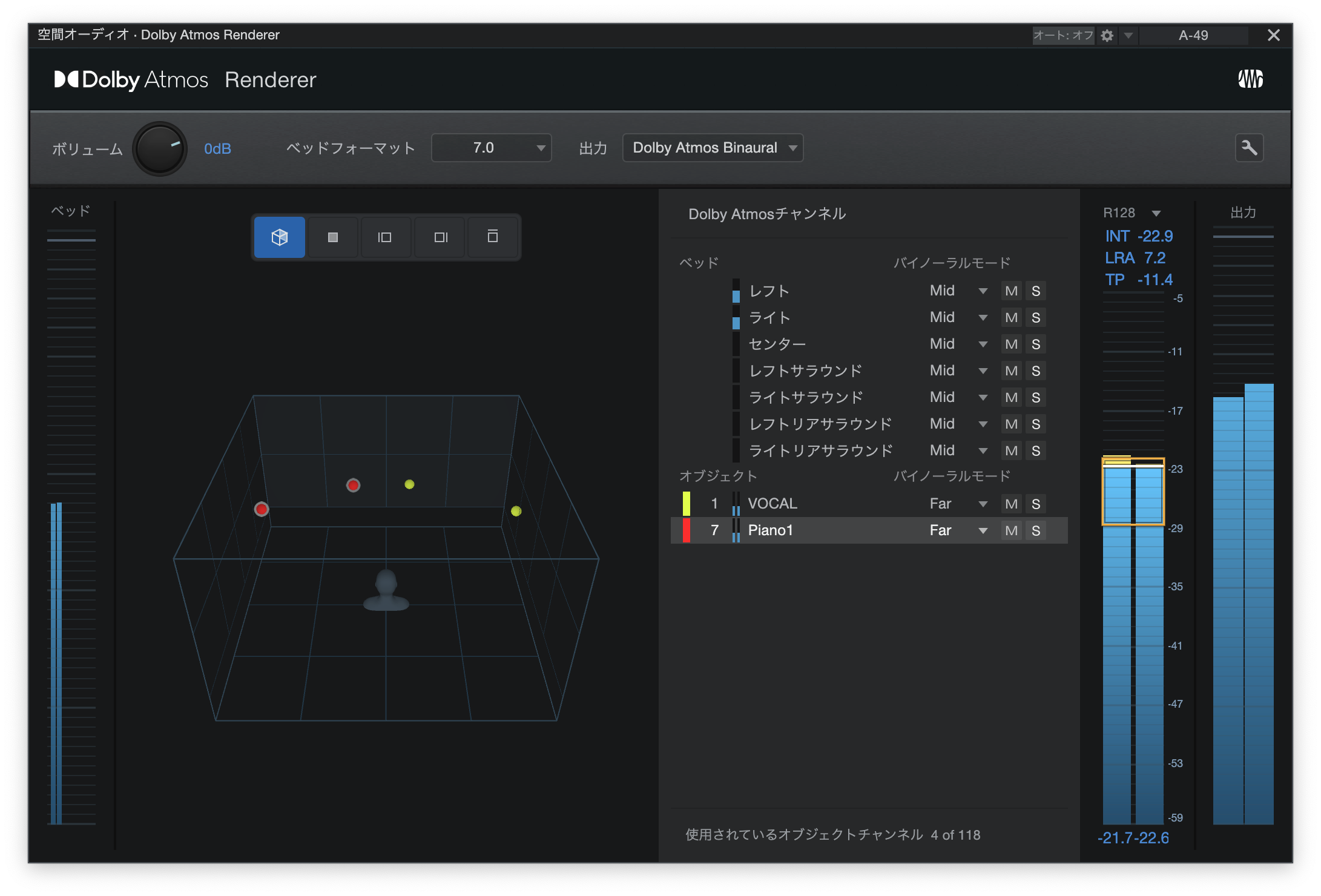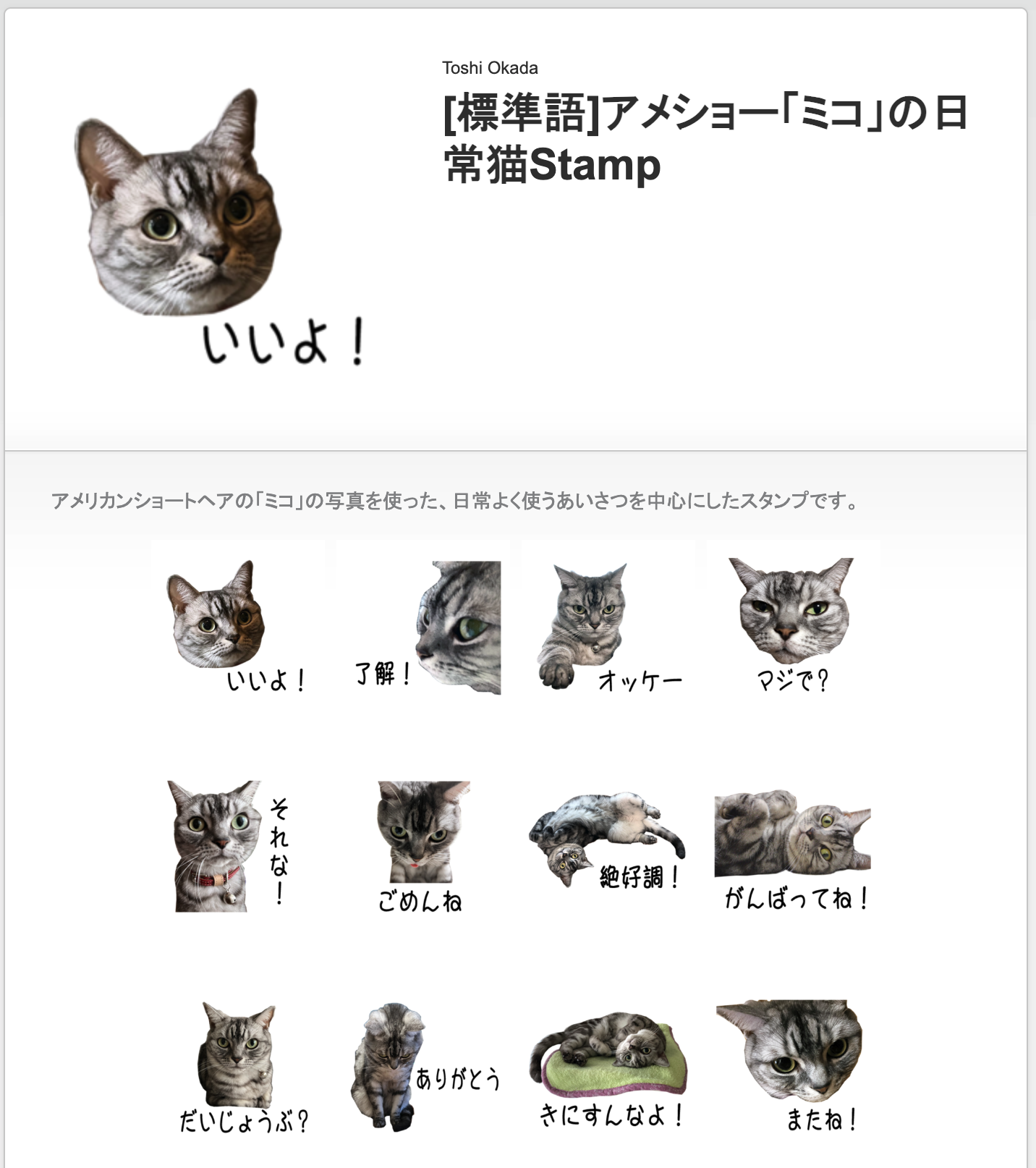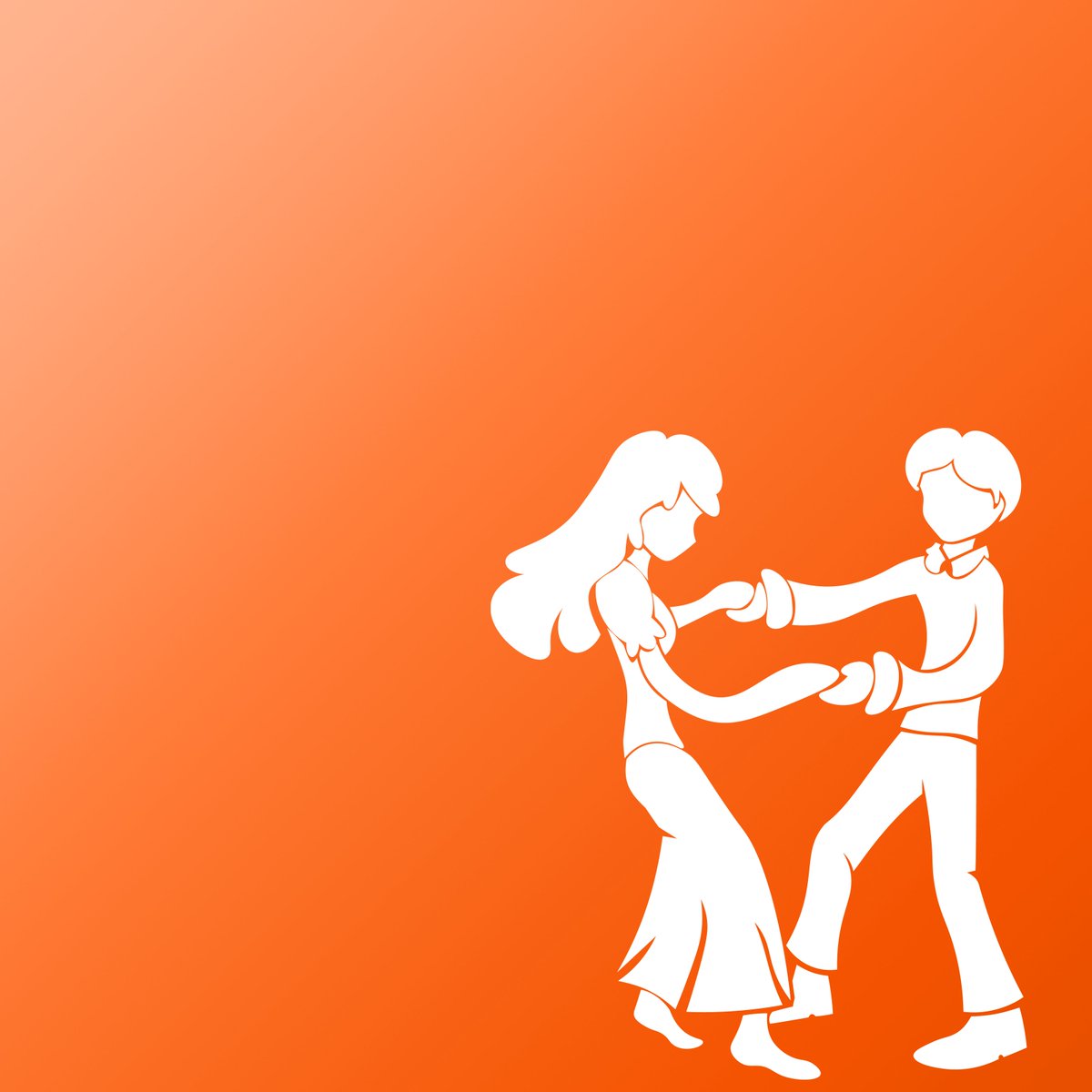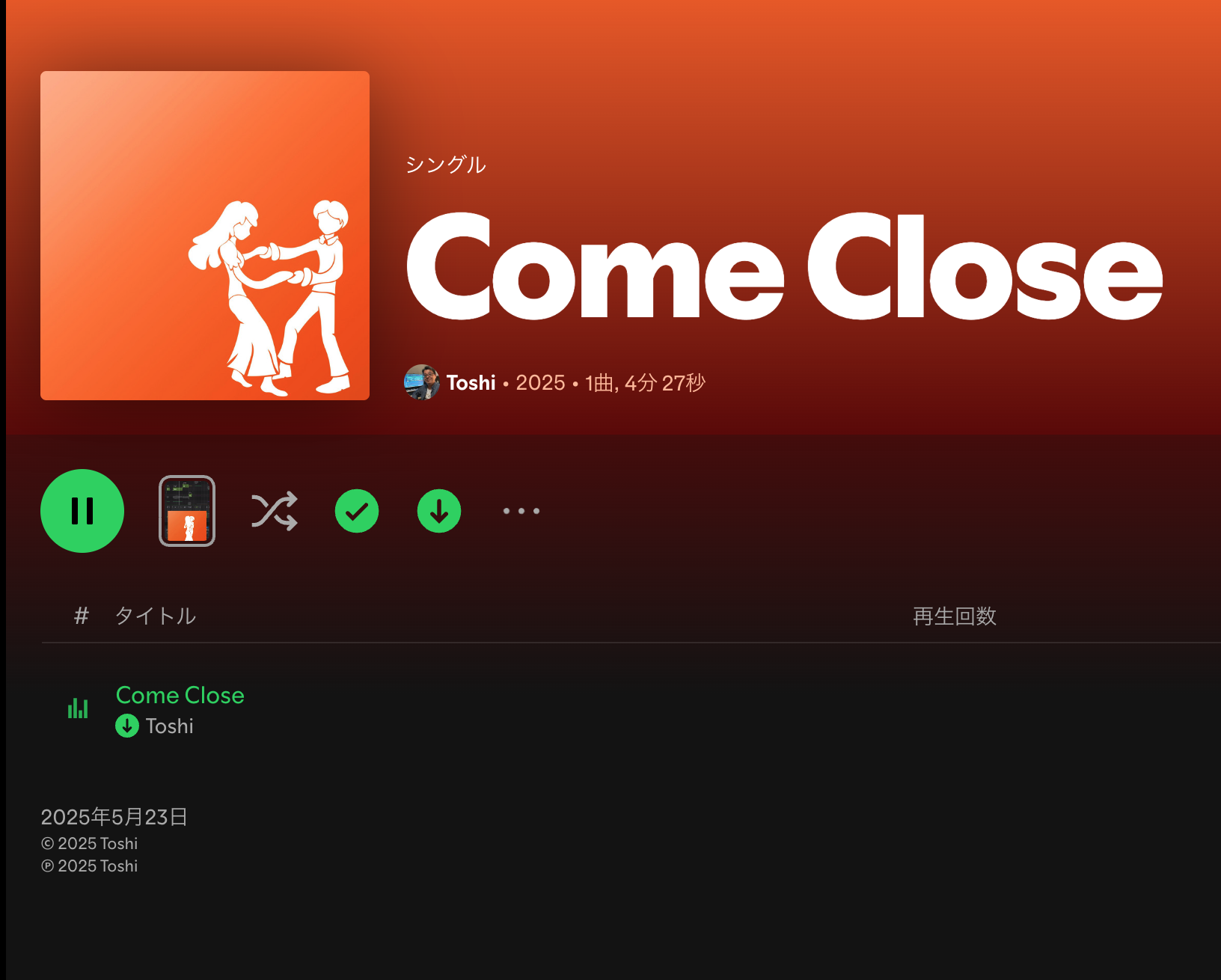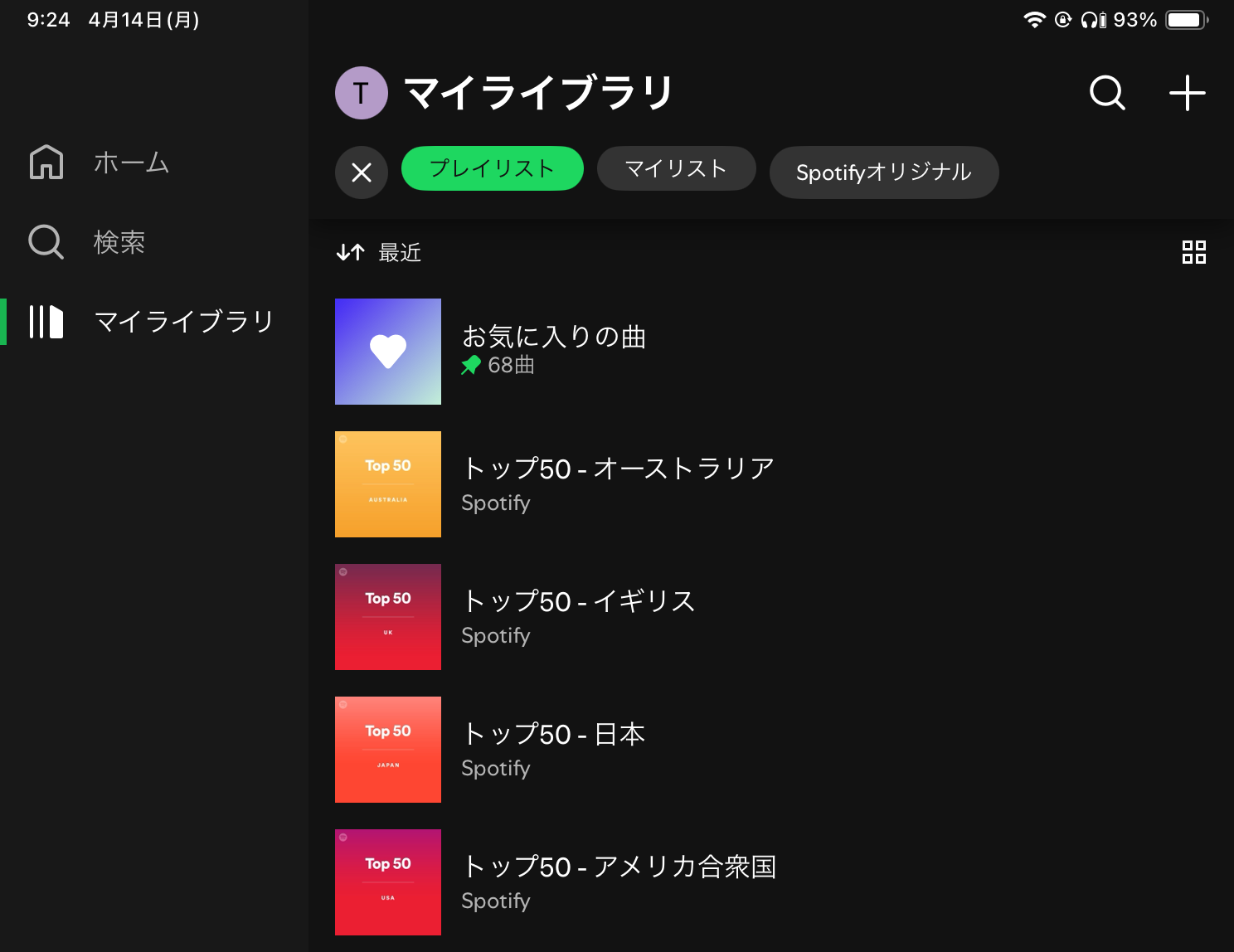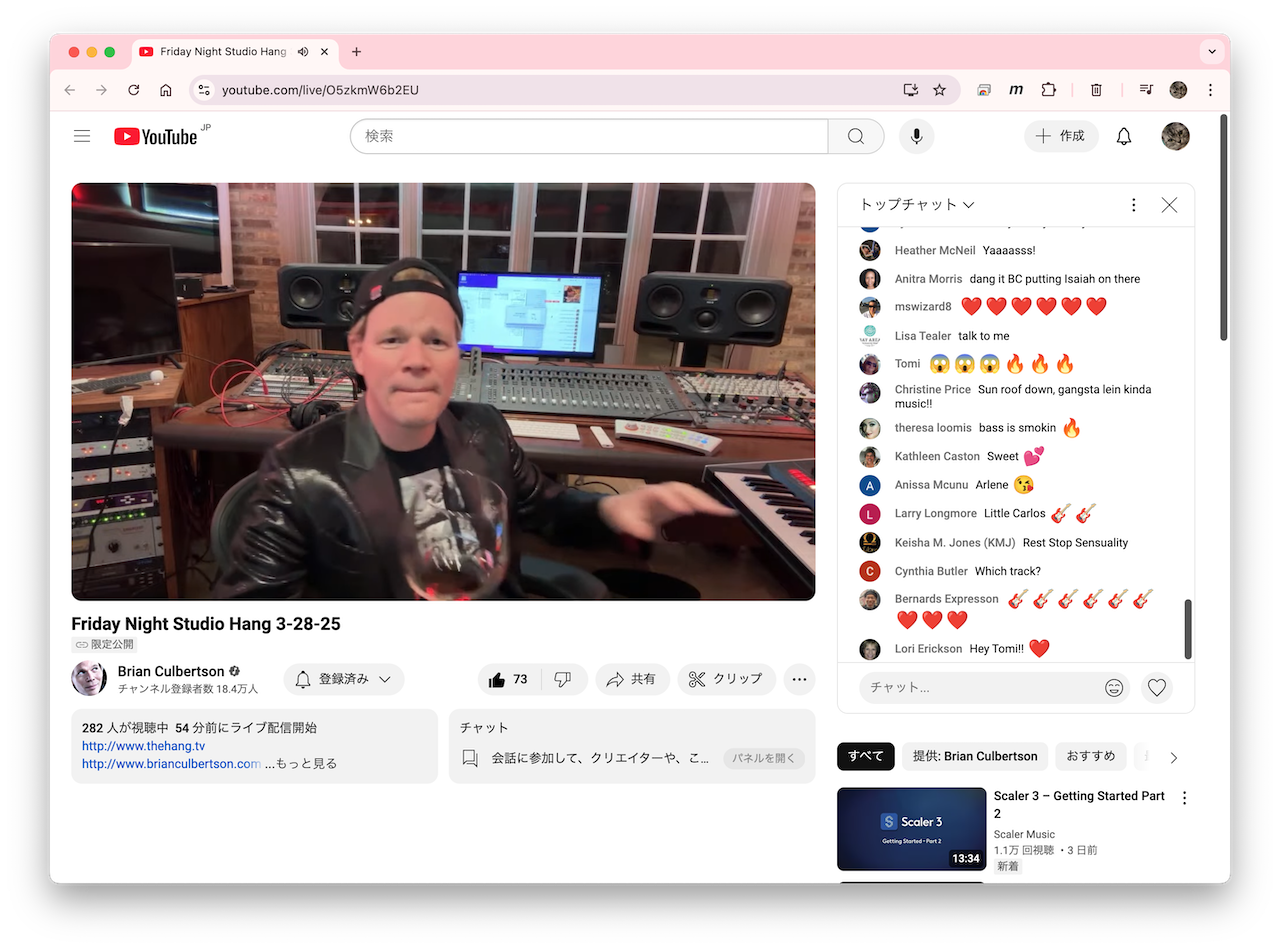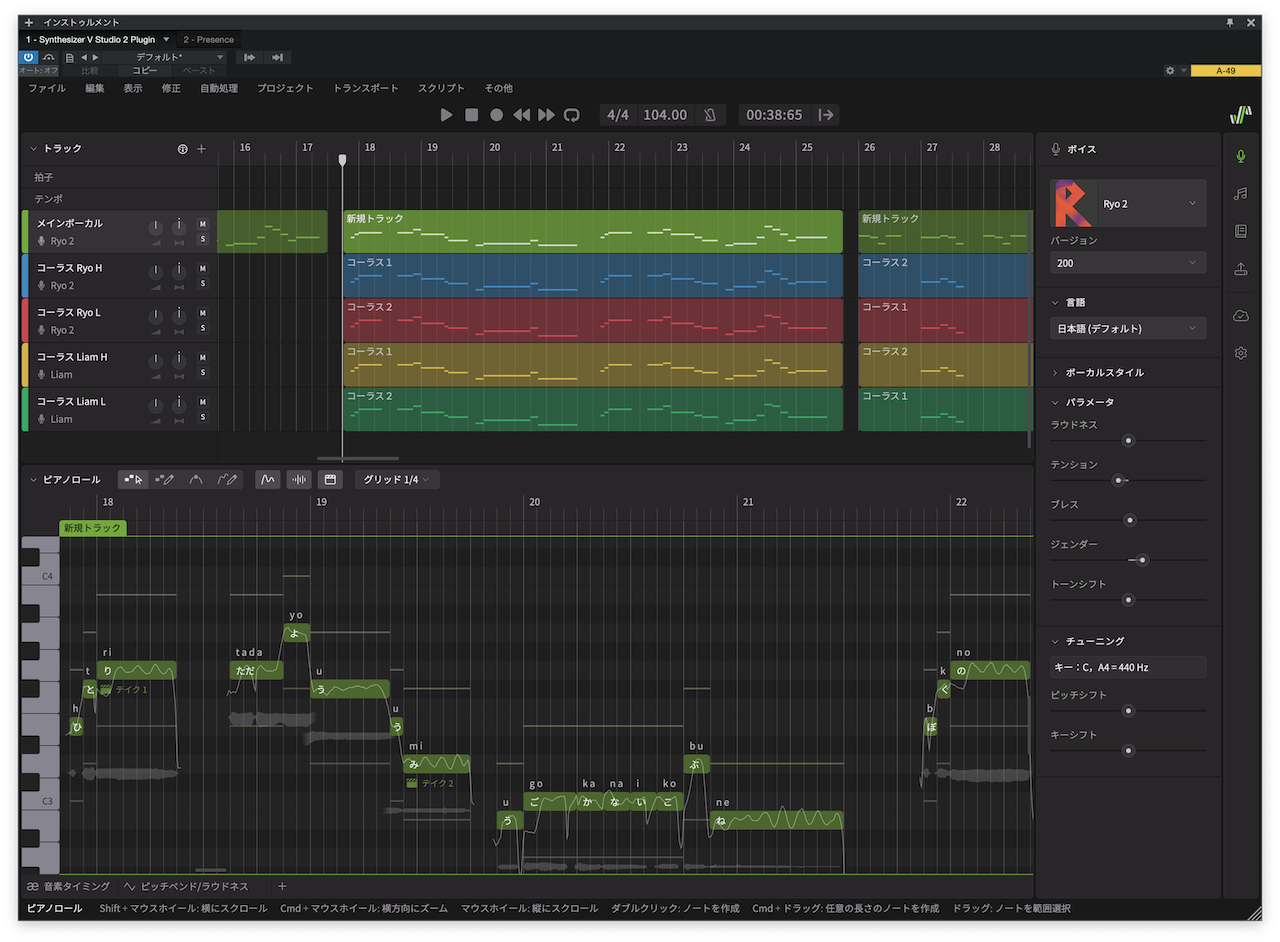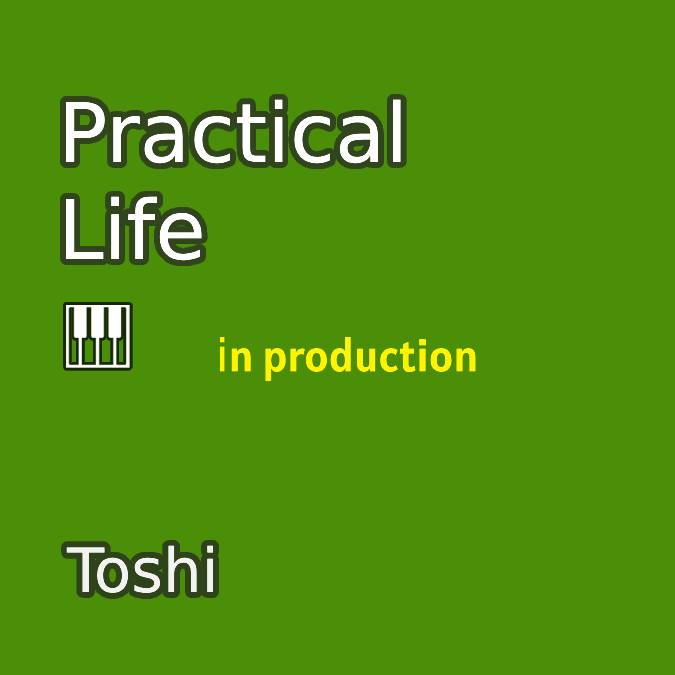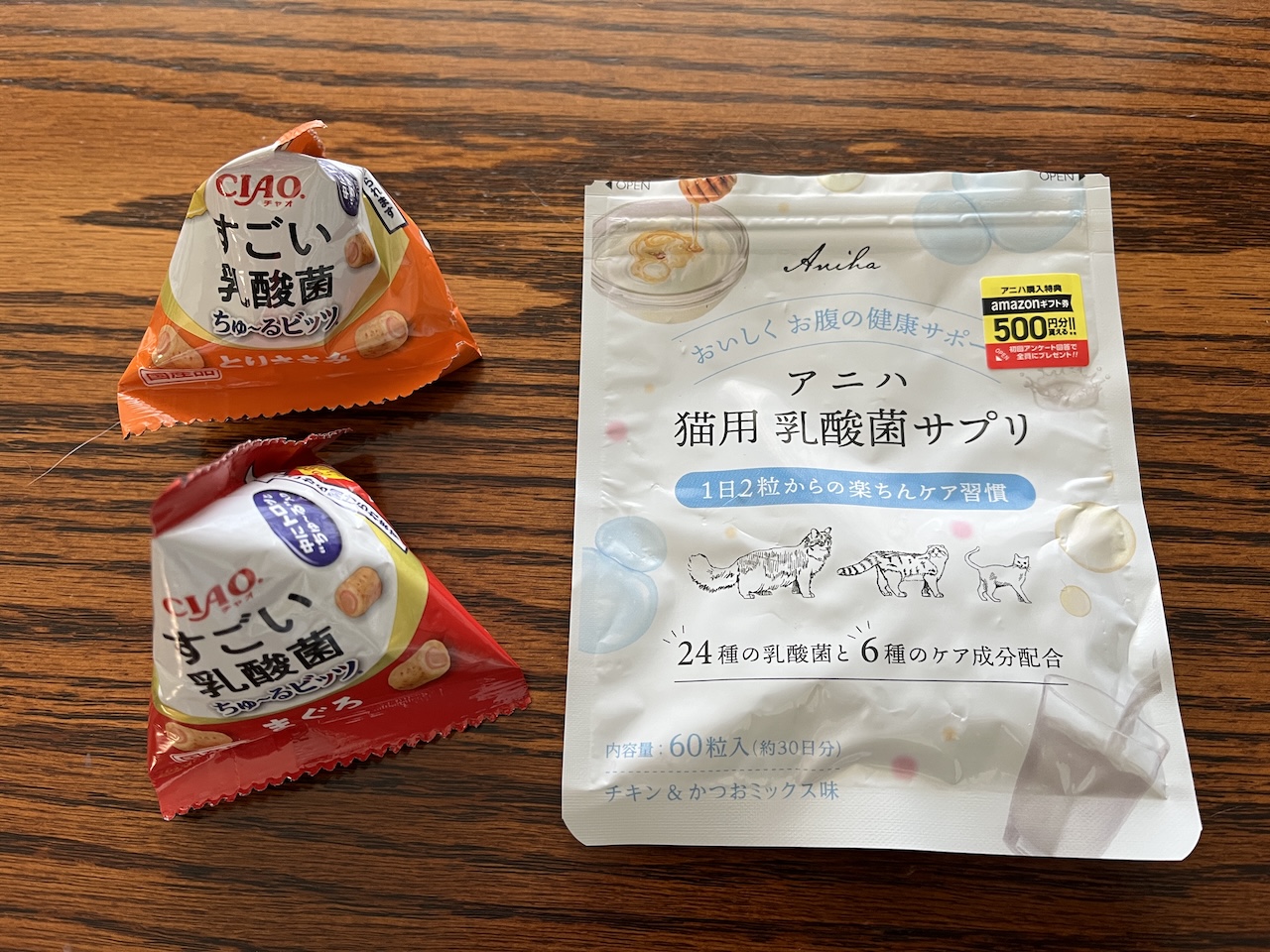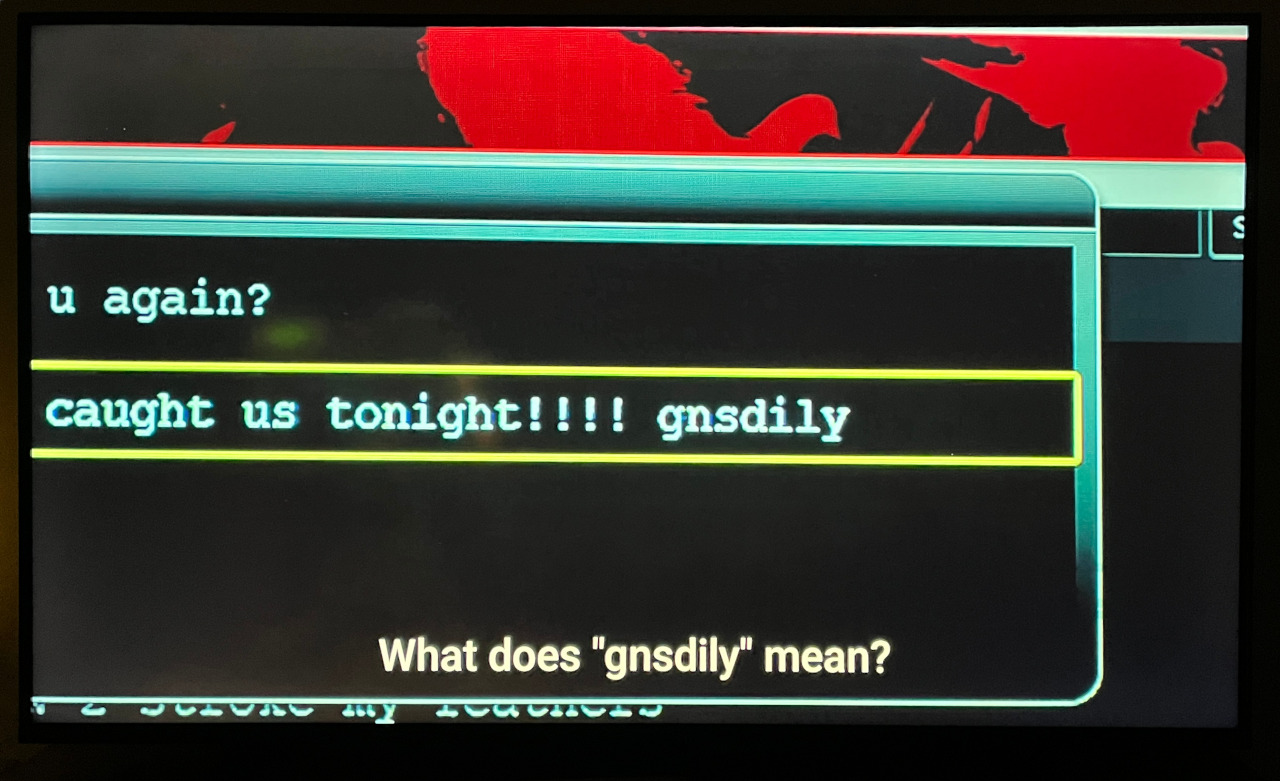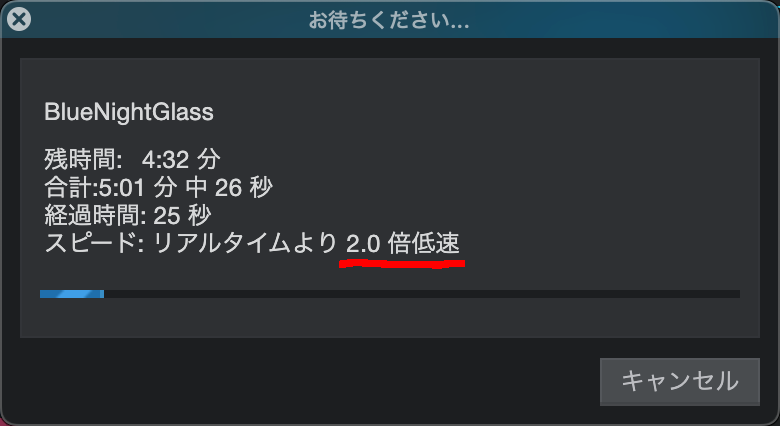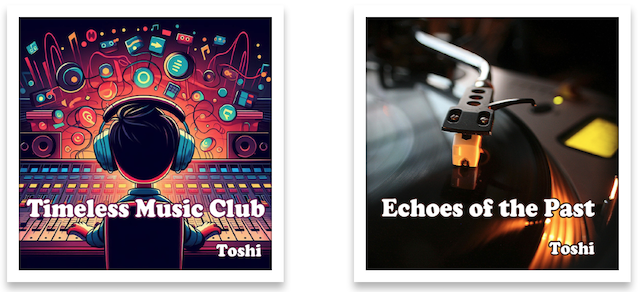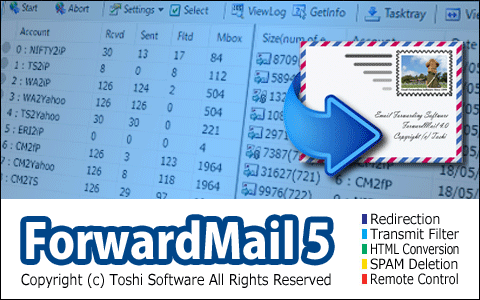● ブログトップページ(このページ)
[ホームページリンク]
● ホームレコーディング 楽曲集/宅録/DTM
● 自作ギターエフェクター/ツール/パーツ
● A3サイズのNゲージ箱庭鉄道模型
[イチオシ記事]
★ 素人の私が英語のPOPソングを作ってSpotifyに配信するまで
最近のブログ
|
|
|
|
良く読まれているブログ
自動集計:2025/07/19-07:00
ブログ一覧表示選択
カテゴリを選ぶ:●ビデオゲーム ●DTM機材 ●ギター/楽器 ●DTMソフト ●音楽鑑賞 ●デジタルギア ●家電 ●ベランダ植物 ●ソフトウエア開発 ●アメショー ●若い頃の興味 ●鉄道模型 ●オリジナル曲 ●エフェクトペダル ●日常生活
年を選ぶ:
●2025年 ●2024年 ●2023年 ●2022年 ●2021年 ●2020年
2025年 07月
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年 06月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年 05月
|
|
|
|
2025年 04月
|
|
|
|
2025年 03月
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年 02月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
●2025年のブログ 続きあります...